来る日も来る日もラインを回し回され、やがてそれが日常となり何も考えなくなってきた頃、一月と六日が過ぎた十一月二十五日。ついにその時が訪れた。心無しか朝からみんなの顔がウキウキしている。僕もわけもなく踊り出したいぐらい身体の裡で喜びが暴れているのを感じていた。
そう、今日は給料日。
朝礼が終わると個別に名前を呼ばれ給料明細が手渡される。普段あまり姿を見せない係長の田原さんがここぞとばかりにその役を買って出ていたが、今は何もかもが微笑ましく、やがて「戸邊はもう一人前だな!これからも頼むぞ」との言葉と共に渡された薄っぺらい明細書一枚がやけに嬉しく、そして重たく感じられたものだ。
これが人生初給料。厳密にはバイトなどの給料は貰った事があったが、初任給と呼ぶべきものは紛れも無く今この瞬間だったろう。すぐにでも明細書を破いてまじまじと内容を見つめたい欲求に耐えながら、一発目の仕事の準備をし、やがて耐え切れず急いでトイレへ行って明細書を破くのだ。
(……っ!?)
破かなければよかったかもしれない。明細書の総支給の欄に書かれた数字に時が止まる。反面で動機は激しくなる。一体なんだこれは。
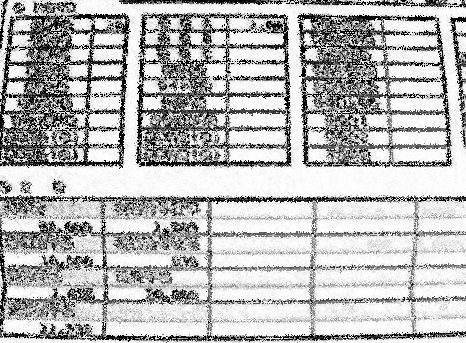
ラインに戻った抜け殻のような僕を見て察したのだろう、大森さんが嬉しそうにこう言ってくる。
「ねえねえ戸邊くん、期待ハズレだったでしょ」
「え、ええ、わかるんすか」
「何でだと思う?お姉さんがそのカラクリを教えてあげよう」
大森さんの話は簡単だった。今日は二十五日。ホンダの給料は月末締めの二十五日払いである。僕が入社したのは十月の十九日。つまり、今回支給された給料は十月の十九日から三十一日までものである。実働たったの十日間。そこに赴任手当てなど期間工の初回ボーナスが多少含まれていたとは言え、なるほど自分で考えていた給料より遥かに少ないわけである。
「月途中で入ってくる人が決まって同じリアクション取るらしいよ」
そういって大森さんは笑っていたが、なんのこっちゃない。勝手に問題解決みたいな顔をしているが、現実に僕が予想していたよりも給料は少なく、この事実は変えようがないのだ。
予定が大幅に狂ってしまった。
実はこのとき給料を抜かした残金は二千円とちょっと。そこに今月の給料十一万一千五百円が加わっても・・・・・・確かに当時の僕には大金ではあるが、一ヶ月の遊び代としては物足りない金額である。
僕はもっと劇的に何かが変わると思っていた。毎日ステーキ弁当を食べても余裕だとか、なんなら風俗に行ってみてもいいなとか。些細な、それでいて今までとは比べ物にならない自由が手に入ると思っていたのだ。
とぼとぼと岐路へ着く。帰りに銀行に寄って五万円を降ろした。これは親に借りた生活費分と、来月までの食費に充てる手を付けられない金だ。ともすると遊べる額は残り五万三千円か。
奇しくも翌日は僕の二十歳の誕生日である。いつもおにぎりを買う天神屋で、量り売りのカレーをこれでもかと目一杯ルーを注ぎ込んだ。目に付いたから揚げにも手が伸びた。抑圧された一ヶ月へのささやかな反抗は千四百円もの代償だった。
(いつもの七倍かよ)
だが、うまかった。憂鬱な気持ちが吹っ飛ぶくらい、普段ロールパンをかりかりかじっている僕には久しぶりの「ディナー」であった。いつぶりかの腹いっぱいの夕飯を食べ、気が大きくなった僕はその足でコンビニに向かいお酒を買って一人きりのバースデイを祝う。
既にコートが必要なぐらい寒い十一月の真夜中。なぜ自分はこんな寒空の下ビールなどを飲んでいるんだろうと思いつつ、シチューエーションとは裏腹にこれが思った以上に良かった。好きなものを好きな時に食べる事が出来る自由は、少なくとも今ここにあるのだ。
──何かが始まった予感がした。
第十四話へつづく。


コメント